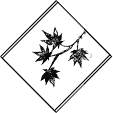
庭付きの家に住みたいけれど、「狭小住宅だから庭は無理かも…」とあきらめている方がいます。でも、あきらめないでください。狭小住宅でも中庭をつくることができます。ただし、坪数が限られているので本当に必要かどうかはよく考えてから決めましょう。ここでは中庭をつくるメリット・デメリット、作り方のポイントを解説しています。
都市部に多い狭小住宅では、庭をつくっても周りの視線が気になります。そんなときは建物の内側に中庭をつくればよいのです。家族だけのプライベート空間ができるため、天気の良い日はカーテンや窓を開けて、庭でバーベキューをしたり、お花を育てたり、好きな時間を過ごせます。緑を植えれば季節の変化を感じることもでき、窓を眺めることで心も癒されます。
部屋を細かく仕切ると窮屈さを感じます。狭小住宅で開放的な空間をつくる方法の一つに、中庭をつくり、中庭に面する部屋に窓を設置することで解放感が出ます。室内から窓を通して中庭に目をやると部屋が広く感じられ、ゆったりくつろぐことができるでしょう。間仕切りを減らすことが「開放感」につながるので、吹き抜けやスキップフロアを取り入れてみるのも良い方法です。
隣家が近接していると、外部に大きな窓を設置することが難しく、周りに高い建物が立っていると日当たりも悪くなります。家の内側の中庭に面した窓から自然光を取り入れると、家の中が明るくなるでしょう。昼間電気をつけなくてもいいので光熱費も削減できます。風の入り口と出口をつくり風通しを良くすれば、心地良い風が部屋の中に入り快適です。自然に空気が入れ替わり換気対策にもなります。
建物の形を箱型の形状にすると建築コストを低く抑えることができます。「コの字」「ロの字」など特殊な形状をしていると、耐震性の補強工事も必要です。その分材料費や施工費がかかるため、建築費用も高くなります。土地代や建築費用を抑えるために狭小住宅を選択しても、中庭を設置することで費用が高くなることを頭に入れておきましょう。
中庭つくると窓の数が増えます。部屋が明るくなったり、心地良い風を感じることができたり良いこともありますが、外気に直接触れる窓は、家の中でも特に熱エネルギーが入ったり逃げたりしやすい部分です。中庭をつくると断熱性が下がり、断熱性が下がると熱が外に出やすく、外からの冷気や熱気が入りやすくなり、冷暖房の効率が悪くなります。
中庭と窓を多く設置する場合は、高断熱にするためにペアガラスやトリプルガラス、樹脂サッシなどを取り入れましょう。
狭小住宅の中庭の坪数は一般的に1〜2坪程度です。雨が降って庭に大量の雨水が流れ込むと逃げ場がなくなり中庭にあふれてしまいます。特にロの字型の中庭は注意してください。中庭に排水経路を設けて排水対策をおこないましょう。掃除をしないで放置していると、枯れ葉が詰まった雨水が排水できなくなるため、定期的なメンテナンスが必要です。湿気がこもるとカビの発生にもつながります。
狭小住宅に中庭をつくるポイントは、ロの字型の設計、室内との空間を区切らない、上の空間を有効活用することです。
建物をロの字型にすると真ん中に空間ができますので、そこに中庭をつくります。居住スペースが狭くなるため、「コの字型」や「L字型」もおすすめなのですが、周りを住宅に囲まれた狭小住宅の場合、中庭に面する全ての部屋を明るくすることができます。また、ロの字型はこの中でもっともプライバシーが守られる形状です。
床面積が限られている中で、中庭をつくることは居住スペースが減ることにつながります。廊下や通路も必要なので、窮屈な間取りになってしまうかもしれません。中庭をつくる場合はできるだけ室内の空間を区切らない間取りにすること。部屋と廊下を一体化させたり、廊下を減らしてスキップフロアで仕切ったりするなどの工夫が欠かせません。
部屋と廊下を一体化すると余分な空間をつくらずに中庭のスペースを確保することができ、廊下を減らしてスキップフロアで仕切れば部屋が広く見えます。
横に広げられないときは、上の空間を有効活用してみましょう。1階建てでは無理でも、2階建て、3階建てと上方に展開していくと、中庭を設置しても十分な居住スペースを確保できます。
中庭を物干しに利用する場合、2階建てにすると人目が気になりません。下着を干すときに気を使わなくてすみ、子どもやペットを遊ばせるときも目の届く範囲で見守ることができます。
狭小住宅でも中庭をつくることは可能です。建物の内側に設置すれば周りを気にすることなくプライバシーも守られ、窓を多く設けると家の中も明るくなります。ただし、建築費用が高くなったり、排水対策とメンテナンスが必要だったりとデメリットもありますので、必要かどうかよく考えてから中庭をつくりましょう。ロの字型の設計や室内との空間を区切らない、上の空間を有効活用するといった中庭をつくるポイントも参考にしてください。